 |
| 平成4年2月15日滑走 |
全国には、
その多くは、姿が富士山に似ていたり、
あるいは、土地を代表する山塊にその名を付けたものもあるかもしれない
この高井富士は、高社山(こうしゃやま)と言い、
地理的には、
この辺りは善光寺平と呼ばれているし、
確かに、周囲は平坦でそんな土地に囲まれて、
古代より信仰の対象とされ、修験道場の跡もあって、
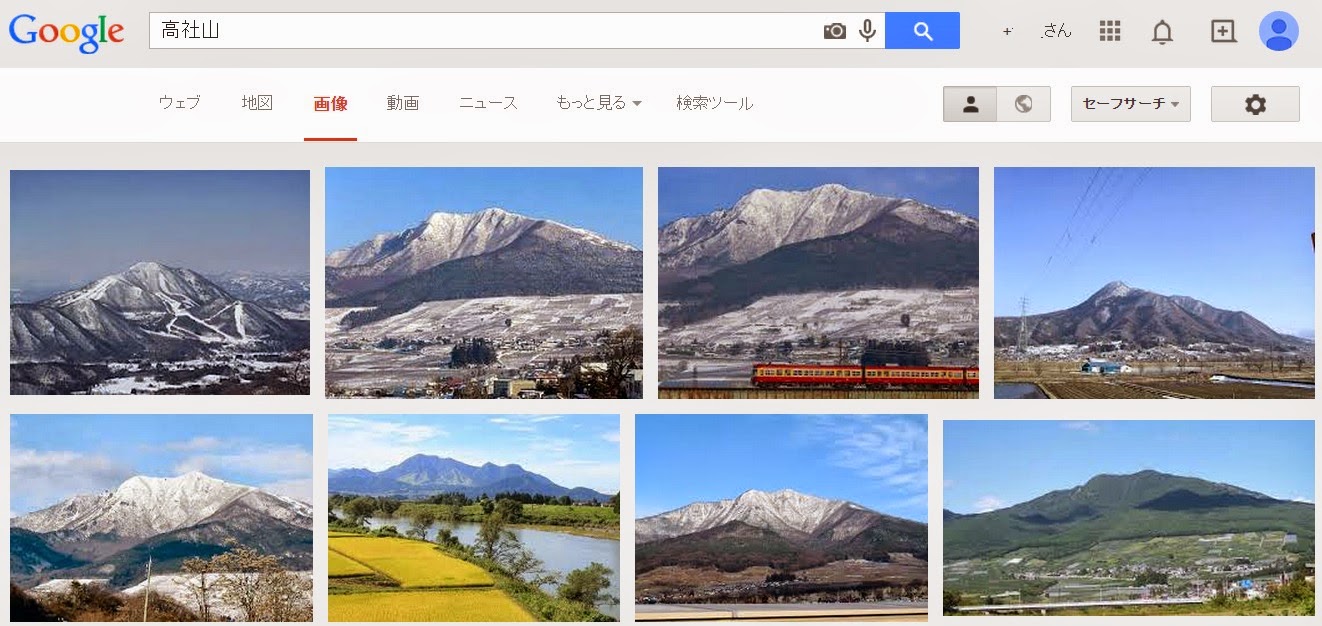 |
| 高社山のイメージ クリックすると拡大します |
ただ、整った円錐形とは言いがたく、
グーグルの画像検索をみると、
おそらく、富士山を容易に拝められない土地ゆえ、
なので、晴れていれば、
さて、この高社山を南北で境にして、
この山以北は、一里を北に行く毎に、
日本海から押し寄せる雪雲が、この山でさえぎられ、
だから、周辺にはスキー場も多く造られて、
先ず、よませ、木島平・牧ノ入は、
一方、志賀高原の西側斜面は、北志賀ハイツ、小丸山、
 |
| 飯山駅の新旧交差ブログ ”コバQのデジカメ歩き”より転用 |
ただ、志賀高原の印象が強すぎてで、北志賀でのPRは不利でしょうか。
それに、ゲレンデは標高が七百メーターと低く、
シーズン初めの雪不足は問題らしく、人工降雪機が設置されていました。
確かに、表面は天然雪でも、
融けて固まった、ざらつく粒の粗い雪が印象的で、志賀高原と比べてしまう。
それでも、標高を上り詰めるドライブも不要で、
というわけで、半日でゲレンデを滑り終え、
今では、リフトを乗り継いでハシゴできるコースも改めて設定されています。
もうすぐ北陸新幹線もオープンで、十分にアクセスが良くなるでしょう。
こうしてみると、このゲレンデも、
おまけ:
 |
| グーグルドライブはこちらから |
注:コースマップ出典元→オールスキー場完全ガイド’95(
 |
| グーグルドライブはこちらから |
いいねと思ったら、二つポチっとね!
0 件のコメント:
コメントを投稿